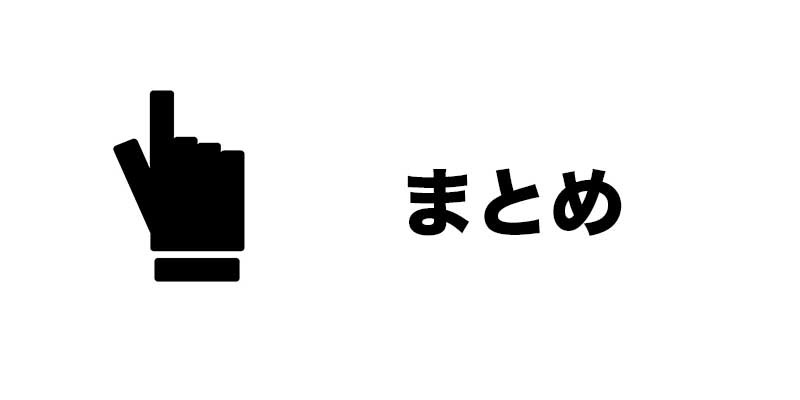壁や天井の「下地」とも呼べる石膏ボード施工は、完成してからは見えなくなる縁の下の仕事です。しかし見えないからこそ、仕上がりに大きく影響します。私自身、何度も現場で実感している重要ポイントをまとめました。
目次
■ 石膏ボードの特徴
■ 施工前の下地確認と準備
■ 石膏ボードの張り付けポイント
■ 継目の目地処理と仕上げ
■ 出隅・入隅の処理
■ 施工後の掃除も大事
■ まとめ
石膏ボードの特徴
現在の東京の住宅やビル内装では、木造・鉄骨を問わず石膏ボードが使われることが一般的です。
私も現場で「やっぱりボードだな」と感じる特徴を列挙します。
不燃性
火事でも燃えず、有毒ガスも出ません。万一の火災時に心強く、壁としての安全性を高めます。
防火・耐火性能
ボード内部に水分が含まれていて、火が当たると水蒸気となって放出される仕組みです。簡単に言えば、スプリンクラーのように火を抑える効果があるんですね。
遮音性
石膏ボードには音を吸収する特性があります。隣や階下への音漏れを防ぎ、プライバシーや静かな住環境に役立ちます。
断熱性
熱伝導率が低いため、東京の夏の冷気や冬の暖房熱を室内に留めます。空調効率を高め、省エネにも貢献するので、快適さを追求するお客様にはよくアピールします。
寸法安定性
温度や湿度で反りにくく、サイズがほぼ一定です。これは壁紙(クロス)を貼る下地には理想的です。施工後のひび割れや隙間が起きにくく、長く美しさが保てます。
これらの特徴を最大限に活かすためには、適切な石膏ボード施工が欠かせません。では、現場でどんな点に気をつけているのか、一つひとつ見ていきましょう。
熟練の職人による最高級の仕事
ボード仕上げならKIREI produceへ!ボード仕上げの経験豊富な職人同士のネットワークを持つKIREI produceが、全国どこの地域でもご対応いたします!また、何かあった場合も安心!ご依頼時のお見積もりから工事後のフォローにいたるまで、KIREI produceがしっかりと丁寧に対応させていただきます。
施工前の下地確認と準備
石膏ボードを貼る前に、まずは下地(木や鉄骨の骨組み)が正しく組まれているか確認します。骨組みの間隔や位置は規格が決まっているため、不足があれば職人に補強してもらいます。
また、電気配線や配管工事が完了しているかの確認も重要です。東京の現場では、築年数が古いと配線が後付けだったりすることがあるので要注意です。
配線・配管が途中だと、あとから再工事が必要になってしまいます。
石膏ボードの運搬と保管についても気を付けます。ボードは重さがありつつも、角が欠けやすく折れやすい素材です。現場で乱暴に扱うと割れてしまうことがあるので、搬入時は慎重に持ち運びます。さらに、石膏ボードは水分を吸いやすい性質があるので、湿気の多い東京では特に注意が必要です。新築の現場やコンクリート打設直後の現場では、湿度が高い場所には置かず、乾燥した場所で一時保管します。
石膏ボードの張り付けポイント
下地が整ったらいよいよボードの張り付けです。一般的にはドリリングタッピンネジやビスで固定しますが、用途や下地によって工法が変わります。
私の経験では、木下地ならビスが基本で、鋼製下地ではクリップ止めも使います。
また、コンクリート躯体へは専用の接着剤で留めることもあります。 張り付けの際には割付け(施工計画)が大事です。
ボードは縦張りか横張りかを決め、開口部(窓やドア)の位置に合わせて切断します。切断後はヤスリで切断面の凹凸を削って平らにするのを忘れずに。ぼろぼろした切り口のまま貼ってしまうと、クロスを貼るときに浮きや凹凸が出る原因になります。
また、施工の基本ですが、ビスや釘は板の表面からほんの少し埋め込むようにして打ちます。
深く食い込みすぎると、そのままクロスを貼った際にくぼみが目立ってしまうんです。必ずビス頭を下塗り用パテで平滑に埋め戻すことがポイントです。
継目の目地処理と仕上げ
石膏ボードを貼っただけでは、板と板の継ぎ目に凸凹が残ってしまいます。このままでは防火性能や遮音性も不十分で、何よりクロスを貼ったときに境目が浮き彫りになってしまいます。そこで継ぎ目の目地処理が必要です。
現場でよく使われる方法は2種類あります。ジョイントボード(テーパーエッジ)では、板の端が斜めにカットされているタイプで、溝が広めです。この場合はまずジョイントセメントで溝を埋め、その上にジョイントテープを貼り、さらに2回パテを塗って平滑に仕上げます。
最後にボード全体に薄くパテを塗って均一に仕上げることもあります。これを行うことで、継ぎ目がまったく見えないレベルにまで仕上げられます。ペイント仕上げや薄手のクロス貼りを予定しているときには、この念入りな仕上げが効果的です。
ベベルボード(ベベルエッジ)の場合は、継ぎ目がV字に細く切り欠かれているタイプです。切り欠きが狭いので、まずグラスメッシュテープを継ぎ目に貼り、その上からパテを2回塗るだけで継ぎ目が隠せます。こちらはテープ+パテ仕上げでシンプルに済ませるケースが多いですね。
私自身、初期のころはジョイントボードでもパテを少なめにして作業を急いだことがありますが、仕上がりの差に驚いた経験があります。「しっかりやった方が手間は増えても見栄えは圧倒的に良くなる」と実感しました。仕上がりが見えない部分ではありますが、ここは手を抜かないよう心がけています。
出隅・入隅の処理
壁の角(出隅・入隅)の部分は傷つきやすく、クロスの浮きや亀裂が起きやすい箇所です。特に東京の住宅では、家具移動の際に角をぶつけたりすることも多いので、しっかり対策します。
出隅:
出隅部分には亜鉛メッキのコーナービード(コーナープロテクター)を貼ります。これで角を保護したうえで、ジョイントコンパウンドを塗って仕上げます。手間にはなりますが、角が真っ直ぐになり、見た目もきれいです。
入隅:
入隅は角が内側になる部分です。この部分も継目と同様のパテ処理を行いますが、特に丁寧なコーナー仕上げを意識します。入隅専用のビード(入隅ビード)を使うこともあります。
施工後の掃除も大事
施工が終わったらホコリと粉の掃除を徹底します。石膏ボードを切断すると大量の石膏粉が出るので、掃除を怠ると後工程のクロス工事で悪影響が出ます。私の経験では、清掃が雑だとクロスの接着不良や施工不良につながることがよくあります。最後に細かい粉まできちんと掃除機や養生で除去することで、クロス貼りもスムーズに進みます。
まとめ
石膏ボード施工では、目に見えない下地処理が美しい仕上がりのカギを握ります。適切な取り付けと丁寧な目地処理・コーナー仕上げを行うことで、防火性能や遮音性もきちんと発揮され、クロス(壁紙)もピンときれいに貼れるようになります。東京のマンションや戸建ての現場でも同様で、「内装後に見えなくなる部分だからこそ丁寧に」が私の鉄則です。
業者として一言。ボード仕上げの工程は華やかさこそありませんが、後から後悔しないためにも非常に大切です。施工を依頼するときは、職人が細かいところまで気を配ってくれるかどうか、ぜひチェックしてください。経験豊富な職人ほど、こうした“見えない部分”の仕事にこだわります。
万全のフォロー体制も売りの一つ!
KIREI produceはボード仕上げ工事を承っております。
職人同士の全国ネットワークを持つKIREI produceは、あらゆる地域からのご要望に対応できる他、何かあった場合のフォローも手厚く安心です!また、特殊な形状のボード仕上げ工事のご相談もお受けしております。
コストパフォーマンスで高い評価を受けているKIREI produceのボード仕上げ工事をぜひお試しください。